活動内容説明
前回のビオトーププロジェクトでは、カブト虫の卵や幼虫をカブト虫園に放したり、恩田川の水質検査を行ないました。今回はカブト虫園の幼虫がどのくらい成長したか確認したり、トンボ池の水質は恩田川や殿山の森のわき水と比べてどうかなど検査薬を使って調査します。
校長先生が今日の活動内容を説明します。
・カブト虫園から幼虫を取り出して、天秤で重さを測ること。
・成長の様子を観察図にまとめること。
・低学年はトンボ池の水、高学年は恩田川の水と殿山の森のわき水の水質検査を行なうこと。
大人たちは子ども達の観察に使うテーブル、上皿天秤、双眼実体顕微鏡などの準備をします。
カブト虫園
カブト虫園には”左”、”中”、”右”の3つの入り口があります。”左”と”右”には子ども達が家で育てた幼虫も放しました。
でも”中”には放していません。
”中”にいるのは、カブト虫が卵を産んで、その卵からかえった幼虫です。
幼虫を取り出す
カブト虫園に移動します。
幼虫は大きく育っているのでしょうか?
”せーの”でフタを開けてみます。

子ども達がいっせいに中を覗き込みます。
校長先生も中を覗き込みます。

シイタケのほだ木や止まり木を外に出します。
ほだ木を見ると、なんと、カブト虫の幼虫が中に沢山はいっていました!”ワー”と歓声が上がります。
これには大人も子供もビックリ。
木の中にいるのはクワガタの幼虫だけではないのですね。

皆でじっくり観察します。
クワガタの成虫も発見しました。

カブト虫は成虫になってから1ヶ月しか生きられませんが、クワガタの成虫は3~4年生きるものもいるそうです。
ほだ木にはやわらかく栄養が沢山あるので、食べるために中に入ったのでしょうと小池さんが教えてくれました。
ほだ木の中に入り込んだカブト虫の幼虫です。
栄養が豊富なのでまるまると太っています。
幼虫の観察
幼虫をシャーレに乗せ顕微鏡でじっくり観察します。幼虫を天秤に乗せ、重さを測ります。
低学年の子供達にはちょっとむずかしいようです。
長井先生がやり方を教えてくれます。
幼虫の観察図を描きます。
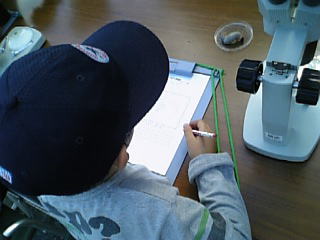
校長先生に結果や感想を報告します。
「重さは大体20グラムくらいだった。」
「幼虫はちょっと気持ち悪かった。」
「幼虫に血管が通っているのが見えた。」
トンボ池でエサあげ
トンボ池の生き物にエサをあげます。金魚がメダカがエサを食べに集まってきました。
よく見ると手長エビもエサを食べにきていました。
水質検査&看板の修復
高学年の子供達は殿山の森のわき水の水質検査をします。低学年の男の子はトンボ池の水質検査をします。
女の子は色あせてしまった看板の色を修復します。
見事看板は色鮮やかになりました。

検査薬を使って水質を検査します。
検査薬には3種類あります。
PH: 水が酸性かアルカリ性か調べる。
空気が汚いと酸性雨が降る。
COD: 水の酸素が十分か不足か調べる。
酸素が多いと汚れが分解される。
NO2: 水が栄養不足か過多か調べる。
水の中に栄養がないと水草が育たない。 使い方はどれも同じ。

線を抜いて手でつぶして空気を抜いてから、逆さにして水の中で手をはなして水を入れます。
比較表を使って水の状態を調べます。
結果発表
いよいよ結果発表。トンボ池の水は、
PH: 0.2 アルカリ性
COD: 50 酸素不足
NO2: ?
生き物の住めるギリギリの水準でした。
感想
カブト虫の幼虫がほだ木の中に沢山いるのを見て正直驚きました。腐葉土の中にいるものとばかり思っていましたので・・・
でも、よく考えてみれば当然のことなのかもしれません。
カブト虫園に入れたほだ木とは、椎茸栽培に使用した後のクヌギ・コナラの腐食の進んで朽ちて柔らかくなったものです。
腐葉土の一歩手前というところでしょうか?
とにかく栄養満点であることは間違いありません。
つまり、ほだ木とは幼虫にとっての”お菓子の家”。
いつでもおいしいエサにありつける最高の住居という訳です。
”たくましく生きているなぁ”と妙に感心してしまいました。
来年はきっと巨大なカブト虫の成虫が見られることでしょう。
期待がますます膨らみます。