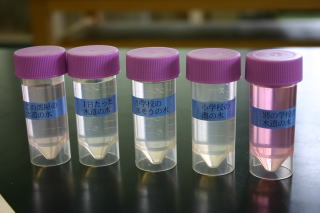活動内容説明
今日のビオトーププロジェクトが始まります。
活動内容は、
- 校庭で剪定した桜の幹にナメコ菌を植えます。
- 前回のビオトーププロジェクトで作った残りの木材を利用して、小池さん、砂長さんが休みに作った7つの巣箱を校庭の木に取り付けます。
巣箱の取り付け
前回のビオトーププロジェクトで作ったのと同じ7つの巣箱を校庭の木に取り付けます。
小池さんがえさ台と巣箱の改造の方法を教えてくれました。
- えさ台の屋根の角度を変えて、面積を広くして雨に濡れにくくする。
- えさが落ちないように止まり木兼、落下防止柵を付ける。
- 観察しやすいように足を付ける。
巣箱のふたがブラブラしないようにネジと針金で固定します。
脚立を使って、校庭のあちこちに分散させて、7つの巣箱を取り付けます。
余りの材料を使って作った巣箱"サイボーグ"を体育館の前の木に付けました。
どんなところに鳥は巣を作りたいのか、を考えながら付けました。
取り付け位置は大人が手の届く高さでも十分です。
こちらは脚立を使って、 高い位置に取り付けてみました。
皆で協力して取り付けます。
子供達も一生懸命結びました。
塩素って知ってる?
「水と塩素と生物」との関係について実験してみます。
森田さんから塩素について教えてもらいます。
塩素っていったいなんでしょう?
塩素は水道水やプールの水を消毒するために使われています。
水は透明だからといって安全ではありません。
目に見えない生物が入っていることもあります。
塩素は病気を起こす小さな生物をやっつけてくれるのです。
今日はどんな水に塩素が入っているか実験します。
皆でプールに水をくみに行ったついでに、プールに沈めた藁を引き上げて、生き物がいるか調べました。
藁の中には赤虫が沢山いました。
水槽の水もくんでから理科室に戻ります。
実験に使う水は
- 理科室の水道水
- 1日おいた水道水
- すいそうの水
- プールの水
- 別の学校の水道水
です。
塩素があると赤くなる薬を使って、水の中に塩素が入っているか調べてみます。
"1. 理科室の水道水"と"2. 別の学校の水道水"が赤くなりました。1日おいた水から塩素が無くなっていました。
塩素は太陽の光にあてたり、分解する薬をつかったり、沸騰させるとなくなるそうです。
塩素は
- 20℃のとき 気体
- そのもののにおいは うすい
※汚れがひどいと結合して嫌なにおいになる。 - 人間に対して 有毒
- 塩素で死なない生物 いる
※クリプトスポリジウム
容器と薬をお土産にいただきました。
自分の家の水道水に塩素が入っているか調べてみます。
ナメコ菌を植える
校庭で剪定した桜の幹にナメコ菌を植えます。ハンマーでナメコ菌のついたチップ(駒:コマ)を埋め込みます。
桜の木にドリルで穴をあけます。
試しに切り株にもナメコ菌を植えてみました。
ナメコ菌を植えた木はお土産に、それぞれ自宅に持って帰ります。
生えてくるのには2年くらいかかるそうです。
一部は校庭に置き、キノコ園としました。
感想
塩素のお話しはとてもわかりやすく面白かったです。
浄水場ポンプの電気代が1日に500万円もかかっていることや、シンガポールが下水道から飲み水を作っていることにとても驚きました。子供も大人も楽しめる内容でした。
学校の校庭に付けられた7個の巣箱。いい感じに付いているので、きっと小鳥が住んでくれることでしょう。
子供から報告を受ける日が来ることを信じて待っています。
キノコ園のナメコも生えてくるか少々不安ですが楽しみです。